近年、子どもたちの遊びの中心はNintendo Switchなどのゲーム機になっています。
そのため、「Switchを持っていない子が遊びに来たとき、どうすればいいの?」と悩む家庭も少なくありません。
実際、ゲームを持っていないことで一緒に遊びづらくなったり、気まずい雰囲気になることもあります。
しかし、工夫次第でSwitchがなくても全員が楽しめる時間を作ることは十分可能です。
この記事では、持っていない子が遊びに来るときにできる配慮や、家庭での具体的な遊びアイデア、トラブルを防ぐ工夫についてわかりやすく紹介します。
親も子も気持ちよく過ごせる環境づくりのヒントとして、ぜひ参考にしてください。
持ってない子が遊びに来るときに考えておきたいこと
この章では、Switchを持っていない子が遊びに来るときに、親や子どもが事前にどのような準備をしておくと安心かを解説します。
事前に話しておくとよい内容
Switchを持っていない友だちが遊びに来るときは、最初に「どんな遊びをしたいか」を子ども同士で話しておくことが大切です。
「Switchで遊ぶ」「外で遊ぶ」「工作をする」など、いくつかの選択肢を出しておけば、みんなが納得しやすくなります。
また、あらかじめ「交代のタイミング」や「順番」「時間の目安」を話しておくと、遊びの途中でトラブルになりにくいです。
親が「今日はこのくらいの時間で区切ろうか」とやんわりサポートするのも効果的です。
お互いが気持ちよく過ごせるようにするには、前もってルールを共有することが何より大切です。
遊ぶルールを決めるとトラブルが減る理由
遊びのトラブルの多くは「時間」や「順番」が原因です。
そこで、遊ぶ前に簡単なルールを決めておくとスムーズに過ごせます。
たとえば、以下のようなルールです。
- 交代制:時間を決めて順番にSwitchを使う
- 持ち時間制限:1人が長く続けないようにする
- 先に決めておく方式:どの遊びをするかを事前に話し合う
タイマーを使って見える形にするのもおすすめです。
ルールを明確にしておくと、「次は自分の番」「終わったら変わるね」と自然に切り替えができ、気まずくならずに済みます。
家でできる遊びのアイデア
ここでは、Switchがなくても家の中で楽しめる具体的な遊び方を紹介します。
ボードゲームや工作など、誰でも参加しやすい方法を中心にまとめます。
ボードゲームやカードゲームの活用
Switchがなくても、ボードゲームやカードゲームを使えば家の中でも十分に盛り上がります。
最近では小学生にも人気のゲームが手軽に遊べて、短時間でも笑いが生まれやすいのが特徴です。
また、みんなで協力して進める協力型ゲームは、対立が起きにくく初めて遊ぶ子でも入りやすくなります。
低学年は絵合わせ系やすごろく系、中学年以降は戦略型や連想ゲームなど、年齢に合わせて選ぶと満足度が上がります。
工作やお絵かきで盛り上がる方法
折り紙や画用紙、のり、はさみなど身近な道具で、テーマを決めて作品づくりをすると自然と会話が弾みます。
「好きなキャラクターを折ろう」「自分たちの街を作ろう」など、設定を加えると創造力を活かした遊びになります。
お絵かきリレーは、1人が一部を描いて次の人へ回す遊びで、完成形の意外性が盛り上がりにつながります。
得意不得意に関係なく全員が参加でき、Switchに頼らない笑顔の時間を作り出せます。
おうちでできる簡単な体を使う遊び
風船バレー、新聞紙の玉入れ、床に線を引いてケンケンパなど、屋内でもできる軽い運動遊びを取り入れましょう。
雨の日や狭いスペースでもできるので、十分にエネルギーを発散できます。
少し体を動かす時間を挟むと空気が和み、子ども同士が自然と打ち解けやすくなります。
外で楽しむ遊びの工夫
この章では、公園や屋外でできる遊びを取り上げ、Switchがなくても充実した時間を過ごすコツを紹介します。
公園や広場でできる定番の遊び
鬼ごっこ、ボール遊び、かくれんぼ、ドッジボールなど、体を動かす定番は自然と参加しやすい遊びです。
「探検ごっこ」や「秘密基地づくり」を加えると、創造力を使った遊びにもなります。
落ち葉集め、木の実拾い、虫探しなど、自然を活かした遊びもおすすめです。
外での体験は、室内では得られない感覚を育てます。
少人数でも楽しめる屋外アクティビティ
2〜3人なら、キャッチボールやフリスビーが気軽に始められます。
紙飛行機を作って飛距離を競う大会や、公園の風景を描くスケッチ散歩も良い選択肢です。
親がヒントを用意する宝探しゲームは、準備が少なくても意外なほど盛り上がります。
外の空気の中で遊ぶ時間は、Switchに代わる貴重な体験になります。
デジタルをうまく取り入れる
完全にゲームを排除するのではなく、スマホやタブレットなどのデジタルを上手に使って、みんなで楽しむ方法を考えます。
スマホやタブレットでできる協力型の遊び
クイズや謎解きなど、みんなで考えながら進める内容を選ぶと全員が関わりやすくなります。
スマホ1台でお題を出して答えるクイズ大会や、自作ショートムービー作りも盛り上がります。
操作役、アイデア役、演技役など役割を分けると、参加している感覚が生まれ、満足度も上がります。
大切なのは「順番交代」と「全員参加」を意識することです。
YouTubeや音楽を一緒に楽しむ工夫
好きな曲でダンスをしたり、工作動画を見て実際に作ったりと、視聴を体験につなげる工夫をしましょう。
子どもが見たい動画を順番にリクエストして流すだけでも、意外と盛り上がります。
視聴で終わらせず、見たあとに何かをする流れに変えると、主体的な時間になります。
音楽や動画は、Switchがなくても共有体験を生み出す道具になります。
トラブルを防ぐためのポイント
最後に、遊びの最中に起こりやすいトラブルや不公平感を防ぐためのルールづくりや親のサポートについてまとめます。
遊ぶ時間や交代ルールを決めておく
最初に「30分ごとに交代」などの目安を決めておくと、無用な揉め事を防げます。
タイマーで可視化すれば、大人が口出ししなくても自然に交代が進みます。
時間割のように「20分室内遊び、20分外遊び」と区切る方法も有効です。
見通しがあるだけで、子どもは落ち着いて過ごせます。
持ってない子へのフォローのしかた
Switch中心になりそうなときは、自然に別案を出して切り替えを促しましょう。
「次は工作にしよう」「外で体を動かそう」など、選択肢を用意して孤立を防ぎます。
Switchを貸してもらったときは「ありがとう」を伝えることを促し、気持ちの良い関係を育てます。
小さな声かけの積み重ねが、場の雰囲気を整えます。
親同士が連絡を取り合う大切さ
遊ぶ前に、親同士で「どんな遊びをするか」「何時まで遊ぶか」を共有しておくと安心です。
家庭のルールはそれぞれ違うため、事前に伝えておくことで誤解を防げます。
お菓子やおもちゃの扱いなど、小さなことでも確認しておくと、当日の迷いが減ります。
迎え時間や休憩タイミングも合わせておくと、スムーズに解散できます。
まとめ
Switchを持っていない子が遊びに来ても、工夫次第で全員が楽しめます。
大切なのは「公平に遊ぶ仕組み」と「代わりの楽しみ方」を用意しておくことです。
ゲームが中心の時代だからこそ、アナログな遊びや体を使う時間は子どもにとって新鮮で貴重です。
親が少し関わることで、子ども同士の関係がより豊かになり、「持ってない=仲間はずれ」ではない温かい関係を築けます。
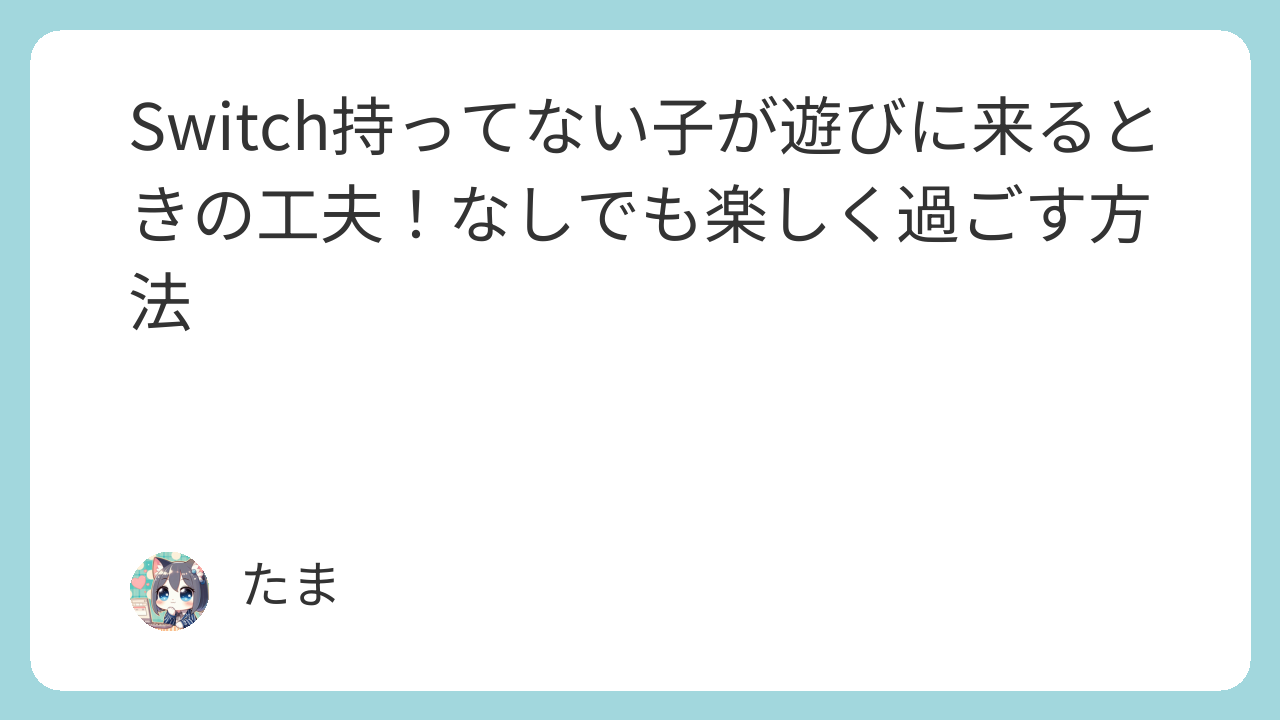
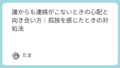
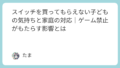
コメント