サンマの塩焼きは、秋を代表する家庭料理のひとつです。
脂ののった身と香ばしい香りは食欲をそそりますが、「焼いたら水っぽくなってしまった」「身がベチャっとしていた」と感じた経験はないでしょうか。
せっかくのサンマも、水分が多すぎると味わいが損なわれてしまいます。
実は、水っぽさにはいくつかの原因があり、調理の前段階から焼き方に至るまでの工程が大きく関係しています。
この記事では、サンマの塩焼きが水っぽくなってしまう主な理由と、失敗を防ぐための具体的な下処理や焼き方のコツを解説します。
美味しく仕上げるためのポイントを押さえ、ふっくら香ばしいサンマを楽しみましょう。
サンマの塩焼きが水っぽくなる原因とは
サンマの塩焼きは、シンプルな料理であるからこそ、仕上がりの違いがはっきりと出やすいものです。
焼き上がりが水っぽくなると、皮はしんなり、身はベチャッとして食感も風味も半減してしまいます。
原因を一つひとつ確認しておくことで、次回からの失敗を防ぐヒントになります。
冷凍サンマの解凍に問題がある
冷凍されたサンマを急いで常温解凍すると、内部に水分が戻りすぎてしまい、焼いたときにその水分が一気に出てしまいます。
その結果、水っぽくなってしまうのです。
冷蔵庫でゆっくり時間をかけて解凍するのが基本ですが、忙しい日にはうっかり室温で解凍してしまうということもあるかもしれません。
私自身も、慌てて解凍してベチャベチャの焼き上がりにがっかりしたことがあります。
焼く前の水分処理が不足している
洗った後の水分や、塩を振って浮き出た水分をきちんと取り除かずに焼くと、蒸気のように身の中にこもってしまいます。
特に皮がパリッと焼けない原因にもなります。
キッチンペーパーで押さえるようにして水気を拭き取るのがコツです。
ここを丁寧にするだけで、焼き上がりの印象は大きく変わります。
焼き方や火加減のバランス
火加減が強すぎると、表面だけが焼けて中が水っぽく残りやすくなります。
一方で、弱火すぎると水分がじわじわ出てきて、べちゃっとした食感に。
中火〜やや強火で、時間をかけすぎず一気に火を通すのが理想です。
最初は強火で表面を焼き固め、後半は少し火を弱めるのもおすすめです。
水っぽさを防ぐ下処理と工夫
焼く前のちょっとした工夫が、焼き上がりの美味しさを左右します。
ここでは実際に自宅でできる簡単な下処理を紹介します。
キッチンペーパーでしっかり拭く
サンマの表面や内臓を取り除いた部分に残った水分を、キッチンペーパーでしっかり拭き取ることが大切です。
水分が残ったまま焼くと、身が蒸されたようになって水っぽくなるからです。
手間はかかりますが、この一手間で仕上がりに明確な差が出ます。
私は魚を焼く前は、調理台にペーパーを多めに敷いて丁寧に拭くようにしています。
塩のふり方で余分な水分を取る
塩は調味の役割だけでなく、余計な水分を引き出す効果もあります。
全体に均一に塩を振って10〜15分ほど置くと、表面に水分が浮いてきます。
それを拭き取ってから焼けば、水っぽくなりにくい仕上がりに。
塩加減が難しいと感じる方は、目分量でなく軽量スプーンを使うと安心です。
冷蔵庫で乾かす時間をとる
塩を振った後、冷蔵庫に入れて5〜10分ほど乾かすと、さらに水分が落ち着きます。
冷たい環境で表面の水分が引き締まり、焼いたときに余計な蒸気が発生しにくくなります。
時間があるときにはこの工程を取り入れると、皮目もパリッと焼けて満足度が上がります。
美味しく焼き上げる調理のポイント
下準備が済んだら、次は焼き方です。
家庭にある調理器具に応じて、工夫できるポイントはたくさんあります。
フライパンとグリルの使い分け
魚焼きグリルは遠赤外線で焼けるため、皮がパリッと焼き上がりやすく、香ばしさも強くなります。
ただし焦げやすい点には注意が必要です。
一方フライパンは火力を細かく調整できるので、初めての人には扱いやすい方法です。
フライパンで焼く際は、クッキングシートや魚焼き専用のホイルを使うと後片付けも楽になります。
皮をパリッと仕上げる火加減のコツ
皮目を下にして焼くときは、中火〜強火で一気に焼き固めるのがコツです。
私は皮目がきつね色になるまでじっと我慢して触らずに焼いています。
途中で動かすと、皮が破れやすく、仕上がりが残念なものになります。
焦げ目をつけつつ中はふっくら仕上げる方法
焦げ目をつけたいけれど、中はふっくら仕上げたい。
その場合、皮目にしっかり焼き色をつけたあと、蓋をして弱火で少し蒸し焼きにすると良いです。
水は入れず、サンマの脂と余熱でふっくら仕上がります。
私はこの方法で焼いたとき、家族から「外はパリパリ、中はジューシー」と褒められました。
秋の献立として楽しむコツ
サンマの塩焼きを主役にするなら、献立全体のバランスも考えると、より食卓が充実します。
サンマの塩焼きに合う副菜
定番の大根おろしは、脂の多いサンマの口直しにぴったりです。
さらに、小松菜のおひたし、きんぴらごぼう、さつまいもの煮物なども相性が良く、秋の食材との調和も楽しめます。
我が家では、さつまいもの味噌汁と合わせることも多いです。
味噌汁やごはんとの組み合わせ
塩焼きには白ごはんが欠かせません。
炊き立てのごはんに、香ばしいサンマの塩気が絡むと、ついつい箸が進んでしまいます。
味噌汁には、豆腐とわかめ、またはしめじやまいたけなど秋のきのこを使うと、香りが加わってさらに季節感が深まります。
旬の食材と一緒に楽しむアイデア
さつまいも、れんこん、かぼちゃなどの根菜類を副菜として添えると、食卓が彩り豊かになります。
秋らしい食材で献立を組むことで、見た目の満足感も高まりますし、季節の移ろいを感じながら食事を楽しむことができます。
まとめ
サンマの塩焼きが水っぽくなってしまう原因には、冷凍や解凍の仕方、下処理の不足、焼き方の火加減など、複数の要素が関係しています。
どれも一見小さなことに思えるかもしれませんが、丁寧に対処することで、焼き上がりの質が大きく変わります。
私自身も、水っぽい仕上がりに悩んでいた一人ですが、今回紹介した工程を取り入れることで、家族にも好評な一皿が作れるようになりました。
ぜひ、ご自宅でもこれらのポイントを参考に、ふっくら香ばしいサンマの塩焼きに挑戦してみてください。
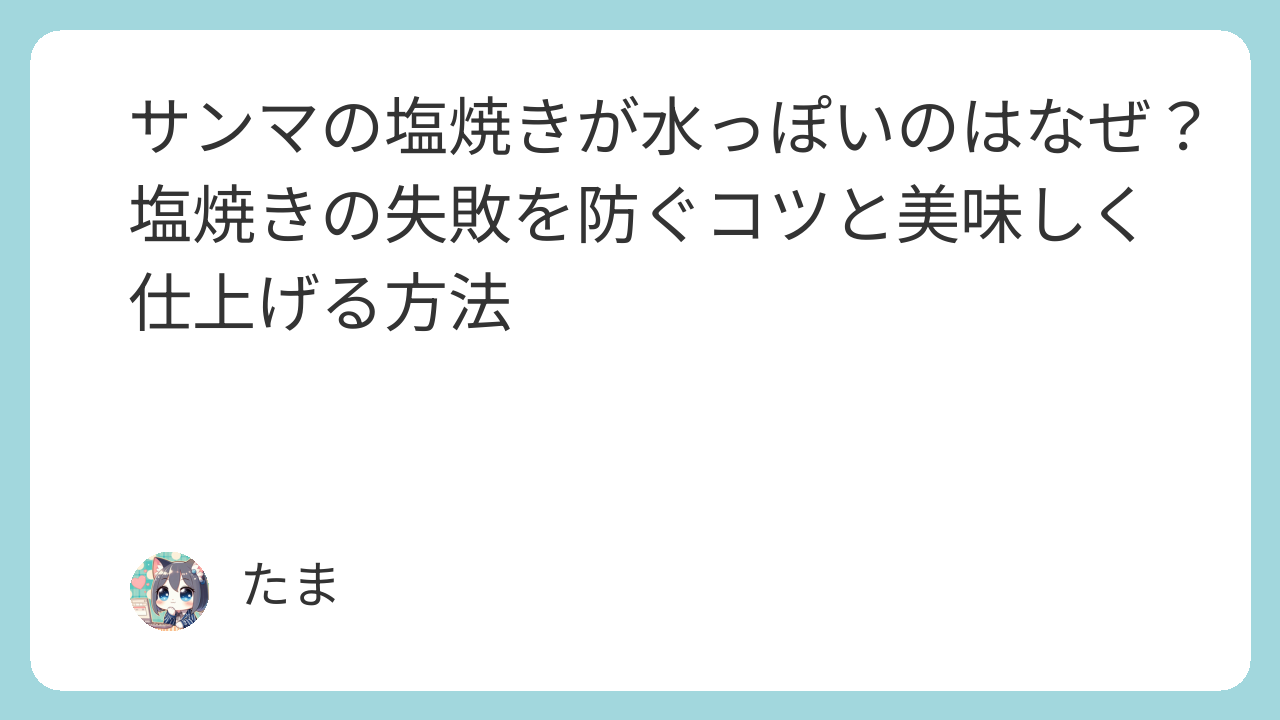
コメント