若者の間で「LINE離れ」が進んでいるという話を耳にしたことはないでしょうか。
これまで日本ではLINEが主要な連絡手段として広く使われてきましたが、最近ではその利用スタイルが変わりつつあります。
「若い子はLINEを使わない」と言われる背景には、どのような理由があるのでしょうか。
そして、LINE以外にどのようなコミュニケーションツールが支持されているのでしょうか。
本記事では、若年層のLINE利用傾向の変化をデータや実例から確認し、代替手段として使われているSNSやチャットアプリについて詳しく解説します。
LINEに対する考え方の違いや、今後のコミュニケーションの可能性を知ることで、より自分に合った使い方を見つけるきっかけになるかもしれません。
若者とLINEの関係を見直す
LINEが若者にとってどのような立ち位置になっているかを確認し、変化の背景を探ります。
最近の若者におけるLINE利用率の動き
日本での最新調査(2023年4月、NTTドコモ モバイル社会研究所)によると、スマホ/ケータイ所有者のうち、15〜79歳の全世代でLINEの利用率が約83.7%という結果が出ています。
10代〜60代で8〜9割がLINEを「月に1回以上利用している」状態です。
ただ、この統計には「所有している」「アカウントを持っている」または「月に1回以上使う」という基準が含まれており、「頻繁に使う」「日常的に使う」「メインの連絡手段として使っている」という意味では、若者の間で使用頻度が減っているという別の傾向も見られます。
例えば、若者がSNSを複数使い分けるようになり、LINEだけではなくInstagram や X(旧Twitter)、あるいはDM・ストーリー中心の利用が目立つようになっています。
さらに、「若者のLINE離れ」という言葉もよく耳にするようになっており、特に20代では、LINEの利用時間や利用頻度がやや減少してきているとの報告があります。
2020年の「若者にLINE離れ?国内最新SNS事情」では、20代の利用時間が微減しているというデータを取り上げ、LINEに常につながっている状態に疲れを感じる人が増えているとも指摘されました。
若者の「LINE離れ」の声とその背景
LINE離れを実感する若者の声としては、「既読無視/既読プレッシャー」「返信しなければという義務感」「グループが多すぎることによる通知過多」「LINEトークの内容・グループ間の雑談に参加することへの負担」「プライベートと公私の境界線が曖昧になること」などが挙げられます。
こうしたストレスから、LINEを開く頻度を抑える・通知をオフにする・返信を遅らせるといった対応をする人が若者の中に増えています。
また、若者の間でプライバシー意識が高まっていることも背景の一つです。
自身のプロフィール・投稿・メッセージがどのように見られるかを意識する世代が、LINE以外のツールの方が制御しやすい・匿名性・非同期性があるものを好むようになってきています。
LINE以外のツールを選ぶ理由と傾向
若者がLINE以外のSNSやチャットアプリを使う理由と、その傾向について解説します。
Instagram DMやストーリーでのやり取り
Instagramは写真・動画の共有が主体ですが、DM(ダイレクトメッセージ)やストーリー機能を通じて、若者同士のコミュニケーションに使われる頻度が高まっています。
ストーリー投稿への反応(リアクション)や、投稿を通じたコミュニケーションが、LINEの「トークを送る/返す」という形とは異なり、気軽なやり取りとして受け入れられているようです。
若者が友人・知人とやりとりする際、「写真や活動を見た・共有したい」が先にあって、それをきっかけにDMでやりとりをすることが多く、単にメッセージを交わすだけのLINEとは用途が少し違ってきている傾向があります。
さらに、初対面やあまり親しくない相手とはLINEではなくInstagramで繋がる方がハードルが低いと感じる人も多いです。
X(旧Twitter)やThreadsの活用
テキスト中心・情報や「つぶやき」の共有が主体となるX(旧Twitter)は、LINEとは異なり即時返信やプライベートグループのような義務感が少ないため、若者にとってストレスが低いコミュニケーション手段とされています。
「トレンドを追いたい」「軽く意見を言いたい」「匿名性を保ちたい」などの目的で使われることが多いです。
Threads のような比較的新しいSNSも、「Instagram との連携性」「フォロー/フォロワーの関係」「公開範囲を限定できる」点で注目されており、若者の中で一定の支持を集め始めています。
これらのツールは、気軽さとプライバシー・コントロール性を両立させやすいのが強みです。
Discord・Telegramなど新しい手段の利用
コミュニティツールとしてのDiscordは、ゲーム・趣味・オンライン活動など共通の興味を持つ人たちとの交流で強みを持っています。
テキストチャットだけでなく、音声/ボイスチャット・画面共有・サーバー/チャンネルでの構造化されたやりとりができるため、用途ごとに空間を分けて使いたい人には適しているという声があります。
Telegram は、日本ではまだLINEほどの普及率ではないものの、セキュリティ・通知オフのしやすさ・パスワード保護や非公開チャット等の機能を評価するユーザーが増えてきています。
「監視されている感じが少ない」「余計な広告が少ない」「履歴管理が自分でコントロールできる」という点で好まれることが多いです。
若者がLINE以外を選ぶ心理とニーズ
なぜ若者はLINE以外のツールを使いたがるのか、心理的な背景を解説します。
気軽さ・返信のプレッシャーを避けたい
若者たちは、メッセージをすぐ返さなければならない義務感や「既読」「未読」による緊張感をしばしば感じており、それがコミュニケーションの楽しさを損ねているという意見があります。
LINE以外だと、返信が非同期的であったり、通知をコントロールできたりするものが多いため、プレッシャーを軽減できるという需要があります。
例えば Instagram DM や Discord のチャットなどでは、それが可能です。
プライバシーと個人情報への意識
自分が誰とどんな情報を共有しているかを意識する若者が増えており、より細かい設定が可能なアプリや機能を求める人が多いです。
Chat ツールの中には、プロフィールを限定公開にできるもの・メッセージの履歴を残さない・通知やスタンプなど余計な機能が少ないものもあり、そういったものが選ばれる傾向があります。
距離感を保った関係性の築き方
友人関係・趣味関係など、多様な人間関係を持つ若者は、LINEのような親しい人との交流だけでなく、遠い存在との交流・趣味や興味でつながる関係にも価値を置くことが多いです。
そういった関係では、無理に返信を求められないツールが好まれることがあります。
さらに、相互の負担を減らすために「見せたい部分だけ見せる」「関係ごとに使い分ける」という使い方が増えています。
LINEが必要な場面と若者の対応
LINEが避けられない場面と、若者がどのように工夫して使っているかを見ていきます。
学校や仕事などでのLINE利用前提の場面
学校・サークル・アルバイト・家庭・地域のコミュニティなどでは、LINEが公式連絡手段または慣習として浸透している場所が多いです。
連絡網・保護者連絡・緊急連絡など、安全・即時性が求められる場面ではLINEが選ばれることが多いです。
若者はこれを無視できない事情として認識しています。
代替ツールとの使い分けの工夫
LINEだけでなく、用途・相手・目的によって複数の通信手段を使い分ける若者が増えています。
例として、親しい友人とは LINE、趣味の仲間とは Discord、SNSでの軽い情報共有には Instagram や X を使う、また通知をオフにしてプライベート時間を確保するなどの工夫があります。
こうした使い分けによりストレスを軽減し、自分の生活リズムに合わせたコミュニケーションスタイルを作る人が多いです。
今後のコミュニケーション手段の可能性
今後はさらに「非同期コミュニケーション」「限定公開/クローズドなチャット」「匿名性」「プライバシー保護」「通知オフの柔軟性」といった機能を重視するツールが若者の間で支持されやすいと見られます。
また、新たなSNS/チャットアプリが日本市場に入ってくる可能性もあり、それらが若者のニーズをどう取り込むかが注目されます。
例えば Discord のコミュニティ機能・Telegram の公開チャネル・Snapchat や BeReal のような「リアルタイム性・限定性」の強い投稿形式などが挙げられます。
まとめ
若者にとってLINEは依然として主要なコミュニケーションツールですが、「使い方」「頻度」「用途」が以前とは変わってきており、若者の中にはLINEをメインの連絡手段とせず、あえて使わない・限定的に使うという選択をする人が増えてきているようです。
その背景には、返信や通知へのプレッシャー、プライバシー意識、コミュニケーションの距離感を保ちたいという心理、「一度繋がると手放せないこと」への疲れなどがあり、若者は自分にとって快適なコミュニケーション形態を模索しているように見えます。
代替ツールとしては Instagram の DM/ストーリー、X(旧Twitter)、Discord、Telegram などが挙げられ、それぞれの特徴を生かして使い分けられています。
結論として、若者が「LINEを使わない」のではなく、「LINEを使うが、使い方をより自由に・ストレス少なく・選択的にする」というスタンスがこれからのコミュニケーションの主流になりつつあると考えられます。
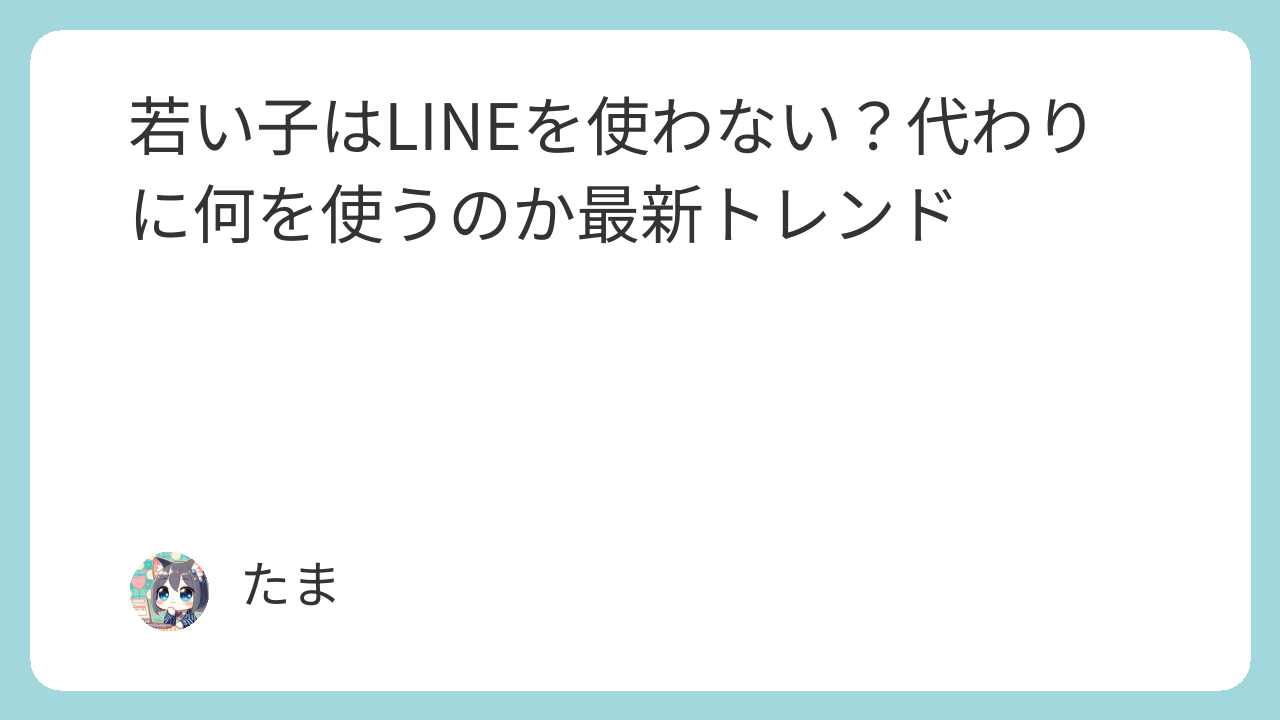
コメント