部屋でゲジゲジを見かけたあと、気づけば見失ってしまった。
「そのまま放っておいたら出ていくのでは?」と考えたことがある人も多いかもしれません。
しかし、本当に放置して問題ないのか、また壁を登るような行動にはどんな意味があるのか、不安が残るところです。
さらに、ゲジゲジの寿命や行動パターンを知ることで、今後どう対応すればいいのかも見えてきます。
この記事では、ゲジゲジを放置したときのリスク、壁登りの習性、寿命や行動周期などを整理し、対策を考える手がかりを紹介します。
ゲジゲジを放置したときの心配ごと
ゲジゲジを放置するとどうなるのか、自然にいなくなるのか、それともリスクがあるのかを考察します。
放っておくと起きるかもしれないこと
見失ったゲジゲジをそのまま放置しておくと、まず考えられるのは活動範囲の拡大です。
餌を求めて動き回るうちに、家具や壁裏、さらには天井裏や床下など、普段目につかない場所に移動してしまうことがあります。
また、餌の元になるゴキブリやクモなどが多い環境では、食べ物を求めて頻繁に家の中を探索するようになり、目撃回数が増える可能性もあります。
さらに、湿気が保たれて隠れ場所に困らない状態が続くと「住みつく」可能性も否定できません。
その結果として、不快感や驚きによるストレス、睡眠不足など精神的な負担が長期化することが懸念されます。
ゲジゲジは自然に出ていくのか
「自然に外に出ていってくれたらいいのに」と思うことがありますが、調べたところでは、ゲジゲジが完全に自発的に家を出て行くという保証はあまり期待できないようです。
むしろ、「越冬場所を探す」「餌を求めて来る」といった行動によって、結果的に姿を見せなくなることはあると考えられます。
例えば、寒くなって動きが鈍くなる時期には隠れやすい場所でじっとして外から見えにくくなるため、「もういない」と思われることがあります。
しかし、エサや湿度がある間は家屋内に留まる要因が多いため、完全な放置は推奨できません。
放置する前に考えておきたいこと
もし「少し様子を見よう」と放置を選ぶなら、まずは家の環境を見直すことが重要です。
湿気がたまりやすい場所があるかどうか、餌となる虫が家に多くいないか、隠れ場所になりそうな家具の配置や物の散らかり具合などをチェックしてください。
見つかった隠れ場所を整理したり、換気や掃除をこまめにすることで、ゲジゲジが落ち着いて暮らしづらい環境を作ることができます。
さらに、見失ってから放置する期間が長くなるほど、恐怖や不安が蓄積しやすくなるので、精神的な負荷も考慮すべきです。
ゲジゲジが壁を登る理由を考える
なぜゲジゲジは壁を登るのか、その行動の意味や仕組みについて調べた内容を紹介します。
壁を登る動きの仕組み
ゲジゲジは滑りやすい垂直面であっても比較的自由に移動できる能力を持っています。
体を支持する脚の数が多く、脚1本1本の付け根や先端が壁面にしっかり接地できるように動くので、凹凸や湿度、素材の影響を受けにくいことが多いです。
実際、壁の表面がツルツルな素材であっても、雨どいの部品・パイプ・外壁の継ぎ目を伝って登ってくることが報告されています。
また、壁を登ることで高い位置から隠れ場所を探したり、安全そうなルートを確保したりすることもでき、床面だけでは到達できない空間を利用できるのがひとつの理由です。
登る場所からわかる行動の傾向
壁をよく登る箇所としては、エアコンの配管が接続されている壁面、雨どい、換気口周辺などが挙げられます。
これらは湿気や微温の変化が生じやすく、ゲジゲジの隠れ場所になりやすいためです。
また、雨の日や湿った気候が続く時期には壁に登ってくる頻度が増えるようです。
「雨で水浸しになったり溺れそうになったりしたので壁に上ってきた」という報告が複数見られます。
さらに、家庭内で壁に沿って移動することは、他の障害物を避けたい・暗いルートを通りたいという行動とも関連していそうです。
壁を伝っていると、床の真ん中よりも安全な気がするという選択がされているのではという見方があります。
壁の上で何をしているのか考えてみる
壁の上で静止しているときは、外敵を避けるためや人の動き・振動が少ない場所を選んでじっとしている可能性があります。
温度や湿度が適していれば、休息場所として選ぶことがあるでしょう。
また、夜が深まるにつれて動きが鈍くなるので、動き回る前の“待機場所”として利用されることも考えられます。
別の部屋への移動を試みているケースや、部屋の温度が高すぎる・湿度が低すぎるなどの環境を避けるために高い壁を使って移動している可能性もあります。
ゲジゲジの寿命と生活リズムについて
ゲジゲジの寿命や、季節ごとの活動パターンから見えてくる特徴をまとめます。
ゲジゲジの寿命はどれくらいか
日本で一般的に見られるゲジ(Thereuonema tuberculataなど)の寿命は、およそ5〜6年とされており、幼虫期を含めて成虫になるまでに約2年を要する種類が多いです。
出典によれば、幼い頃に何回も脱皮を重ね、足の数も増えていく成長期を経て成虫へと成熟すると生涯の折り返し地点と言える時期を迎えます。
成熟後も数年にわたって活動できるため、「一見で見かけて放置すると完全に居なくなるか」という考えは楽観的すぎるかもしれません。
季節によって変わる行動
ゲジゲジは温暖で湿度が高まる梅雨~夏の時期(おおよそ6〜9月)に活動が活発になります。
この時期は餌も多く存在し、夜間や早朝に家屋内へ移動することが増えるため、見かける機会が多くなることが多いです。
逆に冬季は動きが鈍くなり、隠れ場所でじっとして越冬や休眠に近い状態になることがあります。
産卵期は主に暖かい時期にあり、成虫はこの期間中に卵を産みます。
卵から孵化するまでの期間、および孵化後の幼虫期は湿度と温度条件によって左右されるため、地域差が出ることもあります。
寿命を考えた今後の対応計画
寿命が5〜6年ということを踏まえると、短期的な「見ないようにする」対策だけでなく、長期的な予防策を講じることが有効です。
たとえば、住環境を整えて餌や湿気を減らし、侵入経路を封じ、隠れ場所となる家具や物の配置を変えることが長持ちする対策です。
毎年気温や湿度が上がる時期に再確認と点検を行い、「居心地の悪い場所」を作ることで、ゲジゲジがその家に定着する可能性を下げることができます。
今後のためのゲジゲジ対策
ゲジゲジが住みにくい環境づくりの方法と、侵入を防ぐための対策を解説します。
住みにくい環境を作る方法
ゲジゲジは湿気、暗さ、餌となる虫の存在を好む昆虫ですが、逆にこれらの要因を減らすことで生息に適さない環境を作ることができます。
例えば、家屋の換気をよくすること、特に梅雨時や雨続きの時期には窓を開ける、除湿器を使う、湿度をモニタリングすることが助けになります。
家具の配置を整理し、物が重なって暗くなりがちな隙間を減らすこと、床下やクローゼットの裏などの定期的な掃除で湿度や汚れを取り除いておくことも有効です。
侵入経路を封じる具体的手段
ゲジゲジは非常に細い隙間からも侵入が可能です。
玄関のドア、窓のサッシ、換気口、エアコン配管の開口部など、隙間や破れがないかを丁寧に確認しましょう。
見つけた隙間にはすきまテープや網戸の補修、シーリング材を使って塞ぐとよいです。
また、家の周囲にある落ち葉・植木鉢・廃材などの湿った隠れ場所を整理・除去することで、外から家の中に近づくルートを断つことが期待できます。
定期的な点検と掃除で予防
日常生活の中で、家具裏、壁の割れ目、換気口、配管まわりなどを定期的にチェックする習慣をつけましょう。
特に梅雨・夏の時期には湿気がたまりやすく、また餌となる昆虫も活動が活発になるため、掃除や整理整頓を念入りに行うことでゲジゲジの出現を抑えられることが多いです。
また、気温や湿度が上がる前後に環境を見直すスケジュールを作るとよいでしょう。
まとめ
ゲジゲジを放置すると、目立たない場所に移動したり活動範囲が広がったりする可能性があり、「勝手にいなくなる」というよりは「見えなくなる」だけのことが多いようです。
壁を登る習性も、餌を求めたり、安全な隠れ場所を探したりする動きの一環として理解できます。
寿命は約5〜6年とされており、成虫になるまでの年数や環境によっても変わるため、長期的な視点で対策を考えることが必要です。
放置する前に、家の中の湿気・餌物・隙間などを見直すことで、ゲジゲジが長く居づらい環境を作れます。
侵入経路の封鎖や掃除・換気など、日常的な管理が再発防止につながります。
これらを意識することで、ゲジゲジに悩まされる日数を減らし、安心できる居住空間を取り戻せるはずです。
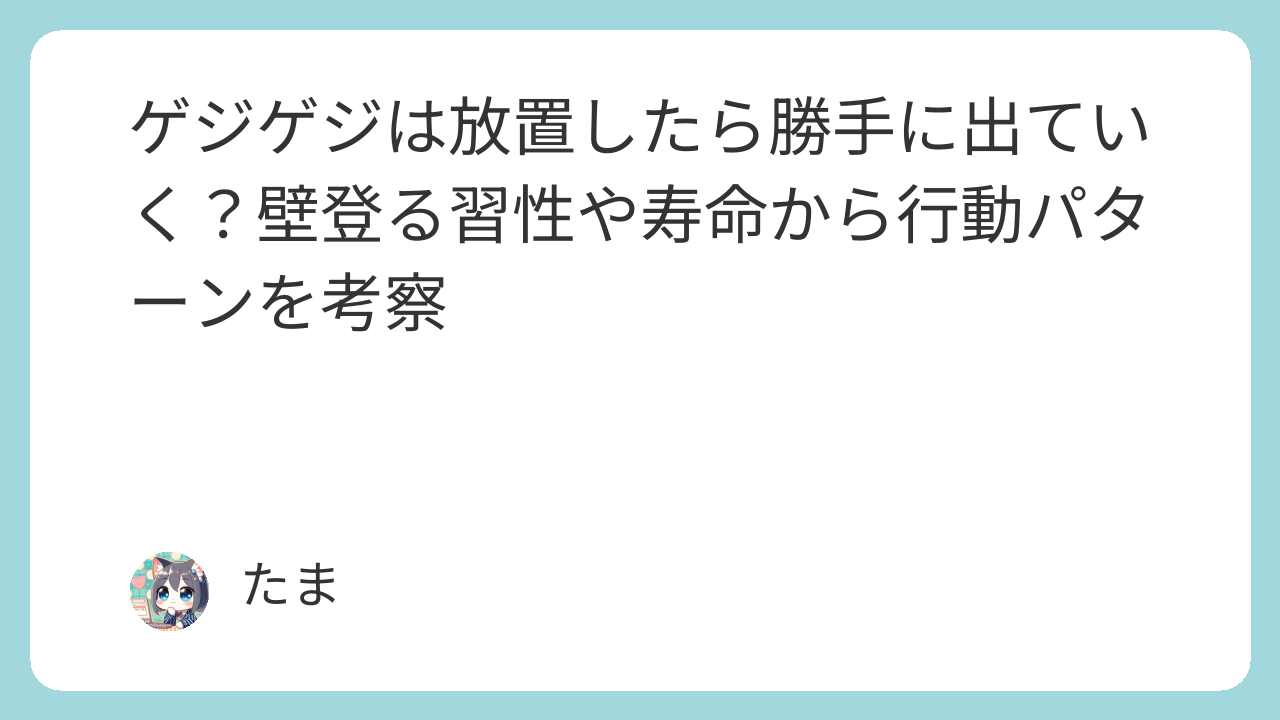
コメント